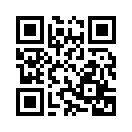2017年05月27日
フッ素の虫歯予防効果って?
子どもに歯が生え始めたら「フッ素で虫歯予防を」とよく耳にするようになった。記者が子どもだった1980年代には、そんなことを聞いた覚えはない。フッ素の効果や適切な使い方を専門家に聞いてみた。【生活報道部・稲田佳代】
「海外ではフッ素は栄養素の一つとして捉えられています」
東京歯科大の眞木吉信教授を訪ねると、最初にちょっと意外な答えが返ってきた。
そもそもフッ素とは元素の一つで、食品や土中、動物や植物に含まれている歯科手術用照明LEDライト。魚介類や海藻は特に多い。自然界では必ず他の元素と結びついた「フッ化物」として存在しているため、あえて言葉を使い分けず、フッ化物を「フッ素」と呼ぶことも多い。ここでも「フッ素」としたい。
虫歯予防に使われる代表は「フッ化ナトリウム」だ。歯は、食事で口内が酸性になるたびミネラル成分などが溶け出すが、唾液によって再石灰化される。フッ素はその再石灰化を促し、歯の表面のエナメル質の成分と結びついて酸への抵抗性を高めることが多くの論文で示されてきたという。
オススメ商品をご覧ください:
日本で虫歯予防に用いられるフッ素は、(1)塗布剤(2)洗口液(3)歯磨き剤――の三つ。(1)は9000ppm(0.9%)と高濃度で、歯科医しか扱えない。(2)は225~900ppmと、毎日使うか週1回かで濃度が違う。口の中でぶくぶくして吐き出すため、うがいができるようになったら使える。以前は医師の処方が必要だったが、昨年9月から薬局で入手できるようになった。(3)は厚労省が1000ppm以下と基準を定めていて、大人用は950ppm程度。1980年代はフッ素が含まれている市販品は1割程度だったが、今は9割以上になった。乳幼児向けは100~500ppm。ただし世界保健機関(WHO)は500ppm未満では虫歯予防の効果が認められていないとしている。

改めて、フッ素が栄養素の一つとはどういう意味なのか。眞木教授に意味を聞くと、厚生労働省が5年に1度発行する冊子「日本人の食事摂取基準」を見せてくれた。健康のために摂取することが望ましい栄養素の推奨量や、健康を害する可能性が高い「耐容上限量」などが示されている。ビタミンAや鉄など大切とされる栄養素でも、取りすぎると害になる。逆に、めっきに使われるクロムなど、有害かと思っていたものも体内の糖質代謝などには必要で「微量ミネラル」の項に並んでいる。
日本の基準一覧にフッ素はない。しかし巻末にある米国と英国の基準一覧には微量ミネラルの項に「フッ素」があった。米国では生後0~6カ月(体重7キロまで)は1日あたり目安量が0.01ミリグラム、上限量が0.7ミリグラムなどとされている。WHOは体重1キロあたり0.05ミリグラムだ。海外では水道水にフッ素を添加することも多く、フッ素のサプリメントも販売されている。食事で体に入るフッ素はあまり吸収されず虫歯予防にはつながらないが、サプリは胃や腸で吸収されやすく加工されており、血液を通じて歯や骨に蓄積されて歯を強くするという。
良いことばかりではない。フッ素は取り過ぎると中毒を引き起こし、嘔吐(おうと)や腹痛、けいれん、呼吸困難などの症状が出る。体重1キロあたり2ミリグラム以上摂取すると、急性中毒の危険性がある。同45ミリグラムで死に至る。
赤ちゃんの場合を考えてみよう。歯磨き剤を使い始める1歳半ごろの体重を10キロとして、急性中毒を起こす量はフッ素20ミリグラム。500ppmの歯磨き剤1本(50グラム)には25ミリグラムのフッ素が入っているので、歯磨き剤1本を丸のみすると中毒になる可能性がある。眞木教授は「気持ち悪くて飲み込めないので、現実的ではない」とする。
一方、歯科で塗布してもらうフッ素は高濃度で、9000ppmと考えると、1回に塗布する2ミリリットル(小さじ半分より少なめ)中に18ミリグラムが含まれていることになる。歯科医は通常、必要分だけ取って塗布するが、「塗布用フッ素がたくさん入ったボトルを患者の目の前に置く歯科医はやめた方がいい」と眞木教授は指摘する。小さな子どもの場合、さっと手を伸ばして取ることもあるためだ。
2ppmを超えるフッ素を含む井戸水などの飲料水を8歳まで継続的に摂取し続けていると、歯に白斑などが現れる「フッ素症」になることもある。虫歯になりにくく歯の機能にも問題はないが、見た目が良くない。ただ眞木教授は、フッ素量が多い井戸水を多用する青森県の一部地域で軽度のものを見たことがある程度で、歯磨き剤でなる心配はないという。
歯は生後6カ月~8歳にエナメル質が形成される。この時期の歯はまだ弱く、虫歯になると進行も早いので予防が大切だ。インターネットで歯のケアについて積極的に発信している「おかざき歯科クリニック」(横浜市戸塚区)の歯科医、岡崎弘典さんにフッ素を使ったケア方法を聞いた。
人間の口内には300~700種類の細菌が生息していると言われるが、生まれたての赤ちゃんの口内には虫歯の原因となるミュータンス菌はいない。大人はまず、感染させないようスプーンなどを赤ちゃんと共有しないことは最近常識になってきた。特に生後1歳7カ月~2歳7カ月は菌が定着しやすい時期なので気をつけたい。
歯科でのフッ素塗布は、歯が生え始めたらやった方が良いという。3歳児健診で虫歯が見つかるケースもあり、遅くとも1歳半には始めておくことを勧めている。
家庭では歯磨き剤を使う。生え始め~2歳は切った爪程度、3~5歳は歯ブラシの3分の1程度を使用し、歯全体に広げる。うがいは1~2回で、フッ素を落とし過ぎないことがポイント。食事のたびに歯は溶けたり再石灰化したりを繰り返しているので、3カ月に1度、高濃度のフッ素を塗布するだけでなく、毎日低濃度で歯磨きをすることが大事だ。もちろん、だらだら食べや甘いお菓子など虫歯になりやすい生活習慣は避ける。
奥歯の溝が深いなど虫歯になるリスクが高い場合は、溝にプラスチックを埋め込んで予防する「シーラント」も効果がある。保険診療で4~5歳の乳歯から施すことができ、虫歯になる可能性を66%低減できるという。
乳幼児が虫歯になったら大人のような治療は難しく、本数が多ければ全身麻酔が必要になる。岡崎さんは「親がしっかりと予防してあげて、歯医者に関わらないでいられるのが一番いい」とケアの大切さを訴えていた。=次回は11月8日に掲載します。
関連記事
「海外ではフッ素は栄養素の一つとして捉えられています」
東京歯科大の眞木吉信教授を訪ねると、最初にちょっと意外な答えが返ってきた。
そもそもフッ素とは元素の一つで、食品や土中、動物や植物に含まれている歯科手術用照明LEDライト。魚介類や海藻は特に多い。自然界では必ず他の元素と結びついた「フッ化物」として存在しているため、あえて言葉を使い分けず、フッ化物を「フッ素」と呼ぶことも多い。ここでも「フッ素」としたい。
虫歯予防に使われる代表は「フッ化ナトリウム」だ。歯は、食事で口内が酸性になるたびミネラル成分などが溶け出すが、唾液によって再石灰化される。フッ素はその再石灰化を促し、歯の表面のエナメル質の成分と結びついて酸への抵抗性を高めることが多くの論文で示されてきたという。
オススメ商品をご覧ください:
http://www.athenadental.jp/category-2082-b0-レンチ式.html
日本で虫歯予防に用いられるフッ素は、(1)塗布剤(2)洗口液(3)歯磨き剤――の三つ。(1)は9000ppm(0.9%)と高濃度で、歯科医しか扱えない。(2)は225~900ppmと、毎日使うか週1回かで濃度が違う。口の中でぶくぶくして吐き出すため、うがいができるようになったら使える。以前は医師の処方が必要だったが、昨年9月から薬局で入手できるようになった。(3)は厚労省が1000ppm以下と基準を定めていて、大人用は950ppm程度。1980年代はフッ素が含まれている市販品は1割程度だったが、今は9割以上になった。乳幼児向けは100~500ppm。ただし世界保健機関(WHO)は500ppm未満では虫歯予防の効果が認められていないとしている。

改めて、フッ素が栄養素の一つとはどういう意味なのか。眞木教授に意味を聞くと、厚生労働省が5年に1度発行する冊子「日本人の食事摂取基準」を見せてくれた。健康のために摂取することが望ましい栄養素の推奨量や、健康を害する可能性が高い「耐容上限量」などが示されている。ビタミンAや鉄など大切とされる栄養素でも、取りすぎると害になる。逆に、めっきに使われるクロムなど、有害かと思っていたものも体内の糖質代謝などには必要で「微量ミネラル」の項に並んでいる。
日本の基準一覧にフッ素はない。しかし巻末にある米国と英国の基準一覧には微量ミネラルの項に「フッ素」があった。米国では生後0~6カ月(体重7キロまで)は1日あたり目安量が0.01ミリグラム、上限量が0.7ミリグラムなどとされている。WHOは体重1キロあたり0.05ミリグラムだ。海外では水道水にフッ素を添加することも多く、フッ素のサプリメントも販売されている。食事で体に入るフッ素はあまり吸収されず虫歯予防にはつながらないが、サプリは胃や腸で吸収されやすく加工されており、血液を通じて歯や骨に蓄積されて歯を強くするという。
良いことばかりではない。フッ素は取り過ぎると中毒を引き起こし、嘔吐(おうと)や腹痛、けいれん、呼吸困難などの症状が出る。体重1キロあたり2ミリグラム以上摂取すると、急性中毒の危険性がある。同45ミリグラムで死に至る。
赤ちゃんの場合を考えてみよう。歯磨き剤を使い始める1歳半ごろの体重を10キロとして、急性中毒を起こす量はフッ素20ミリグラム。500ppmの歯磨き剤1本(50グラム)には25ミリグラムのフッ素が入っているので、歯磨き剤1本を丸のみすると中毒になる可能性がある。眞木教授は「気持ち悪くて飲み込めないので、現実的ではない」とする。
一方、歯科で塗布してもらうフッ素は高濃度で、9000ppmと考えると、1回に塗布する2ミリリットル(小さじ半分より少なめ)中に18ミリグラムが含まれていることになる。歯科医は通常、必要分だけ取って塗布するが、「塗布用フッ素がたくさん入ったボトルを患者の目の前に置く歯科医はやめた方がいい」と眞木教授は指摘する。小さな子どもの場合、さっと手を伸ばして取ることもあるためだ。
2ppmを超えるフッ素を含む井戸水などの飲料水を8歳まで継続的に摂取し続けていると、歯に白斑などが現れる「フッ素症」になることもある。虫歯になりにくく歯の機能にも問題はないが、見た目が良くない。ただ眞木教授は、フッ素量が多い井戸水を多用する青森県の一部地域で軽度のものを見たことがある程度で、歯磨き剤でなる心配はないという。
歯は生後6カ月~8歳にエナメル質が形成される。この時期の歯はまだ弱く、虫歯になると進行も早いので予防が大切だ。インターネットで歯のケアについて積極的に発信している「おかざき歯科クリニック」(横浜市戸塚区)の歯科医、岡崎弘典さんにフッ素を使ったケア方法を聞いた。
人間の口内には300~700種類の細菌が生息していると言われるが、生まれたての赤ちゃんの口内には虫歯の原因となるミュータンス菌はいない。大人はまず、感染させないようスプーンなどを赤ちゃんと共有しないことは最近常識になってきた。特に生後1歳7カ月~2歳7カ月は菌が定着しやすい時期なので気をつけたい。
歯科でのフッ素塗布は、歯が生え始めたらやった方が良いという。3歳児健診で虫歯が見つかるケースもあり、遅くとも1歳半には始めておくことを勧めている。
家庭では歯磨き剤を使う。生え始め~2歳は切った爪程度、3~5歳は歯ブラシの3分の1程度を使用し、歯全体に広げる。うがいは1~2回で、フッ素を落とし過ぎないことがポイント。食事のたびに歯は溶けたり再石灰化したりを繰り返しているので、3カ月に1度、高濃度のフッ素を塗布するだけでなく、毎日低濃度で歯磨きをすることが大事だ。もちろん、だらだら食べや甘いお菓子など虫歯になりやすい生活習慣は避ける。
奥歯の溝が深いなど虫歯になるリスクが高い場合は、溝にプラスチックを埋め込んで予防する「シーラント」も効果がある。保険診療で4~5歳の乳歯から施すことができ、虫歯になる可能性を66%低減できるという。
乳幼児が虫歯になったら大人のような治療は難しく、本数が多ければ全身麻酔が必要になる。岡崎さんは「親がしっかりと予防してあげて、歯医者に関わらないでいられるのが一番いい」とケアの大切さを訴えていた。=次回は11月8日に掲載します。
関連記事
Posted by athena
at 11:19
│Comments(0)