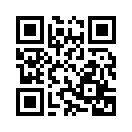2017年04月28日
電動歯ブラシの使い方を誤解していませんか
みなさんは電動歯ブラシを使っていますか? 現在、さまざまなメーカーから多種多様な電動歯ブラシが売り出されています歯科ハンドピース用 カートリッジ。筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、そこで訴えていることの一つが電動歯ブラシの使い方を間違えて歯や歯茎を傷めてしまうケースです。
電動歯ブラシの特徴と使い方

実は電動歯ブラシには大まかに4タイプもの製品があることは意外と知らない人が多いのではないでしょうか。それぞれの特徴や正しい使い方について解説します歯科手術用照明LEDライト。
1.振動式歯ブラシ
数百円から買えるお手頃価格の電動歯ブラシです。往復運動をしますが、振動回数は毎分数千回と低めで、乾電池のものはとくにパワーが弱いのがデメリットです。毛先が歯に直接触れることで汚れを落とすというメカニズムです歯科技工用真空成型器。単純に高速で往復運動をするので、使い方が間違っていると歯や歯茎にダメージを与えることがあります。また、安価なものは替ブラシがなく、使い捨てタイプのものが多いようです。
2.回転式歯ブラシ
歯ブラシが丸い形で回転するタイプのものです。普通の形の歯ブラシでは届きにくい歯の裏側や歯と歯茎の境目、奥歯によく毛先が届くのが特徴です。大きさや振動がやや大きめなのがデメリットです。
3.音波式歯ブラシ
振動式の歯ブラシに音波を発生させて歯垢を除去します。毎分3万〜5万回ほど振動するとされています。毛先を直接歯に当てて汚れを落とすのと同時に、音波の振動による高速水流や発生する細かい気泡が毛先の当たっていない2〜3ミリ離れた周囲の歯垢も落としてくれます。
関連記事
電動歯ブラシの特徴と使い方

実は電動歯ブラシには大まかに4タイプもの製品があることは意外と知らない人が多いのではないでしょうか。それぞれの特徴や正しい使い方について解説します歯科手術用照明LEDライト。
1.振動式歯ブラシ
数百円から買えるお手頃価格の電動歯ブラシです。往復運動をしますが、振動回数は毎分数千回と低めで、乾電池のものはとくにパワーが弱いのがデメリットです。毛先が歯に直接触れることで汚れを落とすというメカニズムです歯科技工用真空成型器。単純に高速で往復運動をするので、使い方が間違っていると歯や歯茎にダメージを与えることがあります。また、安価なものは替ブラシがなく、使い捨てタイプのものが多いようです。
2.回転式歯ブラシ
歯ブラシが丸い形で回転するタイプのものです。普通の形の歯ブラシでは届きにくい歯の裏側や歯と歯茎の境目、奥歯によく毛先が届くのが特徴です。大きさや振動がやや大きめなのがデメリットです。
3.音波式歯ブラシ
振動式の歯ブラシに音波を発生させて歯垢を除去します。毎分3万〜5万回ほど振動するとされています。毛先を直接歯に当てて汚れを落とすのと同時に、音波の振動による高速水流や発生する細かい気泡が毛先の当たっていない2〜3ミリ離れた周囲の歯垢も落としてくれます。
関連記事
2017年04月28日
歯を失ったあの人」に教えたい治療の現実
モデルでタレントの益若つばささんが、自身のツイッターで「歯を出して笑うのが苦手」とツイートしたことが話題になりました。その理由について益若さんは「10代のときに交通事故にあって歯がぐちゃぐちゃになっちゃった」と明かしており、今でもいろんな歯医者に通って歯の治療を続けているそうです。
失った歯を復活させる治療法
益若さんのような不慮の事故に限らず、虫歯や歯周病などによっても歯を損傷したり、失ってしまったりすることは少なくありません。歯科研磨機筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中で紹介していることの1つが、失った歯を復活させる治療法。歯を失った時には、何らかの方法で抜けた部分を補う必要があります。
一般的な処置としては、入れ歯のほか隣り合う歯とつなげるブリッジ治療、人工歯根を入れるインプラント治療があります。ブリッジは抜けている歯の本数によっては選択できないケースがあり、その際は入れ歯かインプラントを選ぶことになります。
インプラントは、失った歯の代わりにチタンでできた人工の根っこを入れて、歯の機能を回復していく治療法です。新しい治療に思われがちですが、実はインプラント治療自体は50年の歴史があり、現在は世界各地で行われ、成功率も95%以上。多くの人が体験している治療です。

インプラントにはどのようなメリットがあるのでしょうか。歯を失った後、奥歯に入れ歯を入れても、もともとの噛む力に比べると約20~30%しか回復できません。一方、インプラントならもともとあった歯のように顎の骨に固定されているために、硬いものでも、くっつきやすいものでも噛めます。
オススメ商品をご覧ください:
http://www.athenadental.jp/category-2068-b0-スリーウェイシリンジ用-ノズル.html
失った歯の部分をブリッジで治すためには、隣り合う歯を削る必要があります。ただ、健康な歯を削れば、その寿命を短くすることにもなります。インプラントなら、隣り合う歯を削らずシンプルに治療できます。口の中の違和感がほとんどないのもインプラントの特徴です。通常、髪の毛一本でも口の中に入れば相当な違和感があるように、金属でできた薄い入れ歯などでも、多少の違和感は否めませんが、インプラントならば、もともとの歯とほとんど変わらない形に回復できるので、違和感はほとんどないといっていいでしょう。
ブリッジでは、失った歯にかかっていた力の負担を土台になる両サイドの歯で補います。それまでよりは、かかる力の負担が大きくなるため土台となる歯の寿命も短くなってしまいますが、インプラントでは、もともとの歯にかかっていた負担を戻せます。
インプラントは歯の根の代わりに人工歯根を使っているだけで、被せ物にセラミックを使えば歯と同じようにすることができます。奥歯の場合は機能面や噛む力によって被せ物や構造を変えることがありますが、前歯はインプラントとは気づかれないようにきれいに治療できます。
インプラントのデメリット
このようにインプラントにはさまざまなメリットがありますが、デメリットも忘れてはなりません。ひとつは治療期間が長いことです。最近ではインプラントも進化し、かなり治療期間も短くなりましたが、それでも短くて2~3カ月、長い場合で6カ月ほどを要します。
また、インプラント治療は、歯を支えているあごの骨に人工の根っこを入れる処置なので、歯茎を開く必要があります。歯科ハンドピース用 カートリッジ、その他症例によっては他にも外科的な処置が必要になってくることもあります。骨粗鬆症や重い糖尿病の患者など、あごの骨に問題がある場合はインプラントができないこともあります。また、極端にあごの骨が痩せている場合などは、人工の骨などを使って、骨を作る処置などが必要になるケースもあります。
さらには先天的な病気などによって歯がないごく一部の場合を除き、インプラント治療を保険診療で行うことはできません。自費診療となるため、平均すると1本35万~40万円ほどの費用が必要になります。
インプラントに関連して、筆者が患者さんからよく聞かれるのは「どれくらいの耐久年数があるの?」という質問です。
インプラントは、入ってしまえば自分の歯とほぼ同じだと考えていいでしょう。手入れさえしっかりすれば自分の歯のように長く持ちます。一生といっても過言ではないかもしれません。手入れとは、毎日の歯ブラシと定期的なクリニックでのメンテナンスです。これさえ、しっかりやっていただければ本当に長持ちします。
ただ、メンテナンスを怠るとこの限りではありません。実はインプラントは、自分の歯のように歯周病(インプラント周囲炎)になることがあります。自分の歯も歯周病で抜かなければならなくなるように、インプラントも歯周病で抜かなければならなくなるケースもあります。
入れ歯のメリットとデメリット
一方で、ブリッジもインプラントもできない場合は、入れ歯という選択肢がありますが、これにもメリットとデメリットがあります。
入れ歯とは歯のなくなった部分に入れる、取り外し式の人工歯の事です。大きく分けて部分入れ歯と総入れ歯があります。また、保険内で作れるものと、保険では作れない自費のものがあります。
入れ歯は、歯が何本抜けていても骨がやせていても作れます。3、4回の通院で作れますのでインプラントほど時間はかかりません。保険が使えれば費用も安く、外して洗えたり、外科手術の必要がなかったりなどといった点もメリットでしょう。
一方で、入れ歯は慣れるまでは違和感があったり、話しにくかったりすることがあります。また、人工歯と歯茎の間に食べかすが入りやすく、食事や話している時に外れることもあります。部分入れ歯の金具が審美的でなかったり、天然歯に比べて噛む効率がかなり落ちたり、金具がかかる歯に力がかかって傷みやすかったりするのもデメリットです。合わない入れ歯を使っていると骨も痩せてしまいます。
それでも、治療費をそれほどかけたくなかったり、外科手術に抵抗があったりする人にとっては、入れ歯は有効な治療法のひとつに挙げられます。口元のハリがなく、老けて見える人やタバコをよく吸う人、短期間で処置したい人などにもお勧めしています。
逆に、入れ歯がどうしても合わなかったり、取り外し式に抵抗があったり、より自然な見た目を求めたりする人にはインプラントが合っています。喫煙もせず、あごの骨がしっかり残っていて、本物の歯に近いかみ応えを求めるような人にも適した治療法でしょう。お口の中の状態、全身の健康状態、求める仕上がりは患者さんそれぞれで異なります。何が自分に合う治療法なのかは、かかりつけの歯科医師とよく相談して決めていきましょう。
関連記事
失った歯を復活させる治療法
益若さんのような不慮の事故に限らず、虫歯や歯周病などによっても歯を損傷したり、失ってしまったりすることは少なくありません。歯科研磨機筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中で紹介していることの1つが、失った歯を復活させる治療法。歯を失った時には、何らかの方法で抜けた部分を補う必要があります。
一般的な処置としては、入れ歯のほか隣り合う歯とつなげるブリッジ治療、人工歯根を入れるインプラント治療があります。ブリッジは抜けている歯の本数によっては選択できないケースがあり、その際は入れ歯かインプラントを選ぶことになります。
インプラントは、失った歯の代わりにチタンでできた人工の根っこを入れて、歯の機能を回復していく治療法です。新しい治療に思われがちですが、実はインプラント治療自体は50年の歴史があり、現在は世界各地で行われ、成功率も95%以上。多くの人が体験している治療です。

インプラントにはどのようなメリットがあるのでしょうか。歯を失った後、奥歯に入れ歯を入れても、もともとの噛む力に比べると約20~30%しか回復できません。一方、インプラントならもともとあった歯のように顎の骨に固定されているために、硬いものでも、くっつきやすいものでも噛めます。
オススメ商品をご覧ください:
http://www.athenadental.jp/category-2068-b0-スリーウェイシリンジ用-ノズル.html
失った歯の部分をブリッジで治すためには、隣り合う歯を削る必要があります。ただ、健康な歯を削れば、その寿命を短くすることにもなります。インプラントなら、隣り合う歯を削らずシンプルに治療できます。口の中の違和感がほとんどないのもインプラントの特徴です。通常、髪の毛一本でも口の中に入れば相当な違和感があるように、金属でできた薄い入れ歯などでも、多少の違和感は否めませんが、インプラントならば、もともとの歯とほとんど変わらない形に回復できるので、違和感はほとんどないといっていいでしょう。
ブリッジでは、失った歯にかかっていた力の負担を土台になる両サイドの歯で補います。それまでよりは、かかる力の負担が大きくなるため土台となる歯の寿命も短くなってしまいますが、インプラントでは、もともとの歯にかかっていた負担を戻せます。
インプラントは歯の根の代わりに人工歯根を使っているだけで、被せ物にセラミックを使えば歯と同じようにすることができます。奥歯の場合は機能面や噛む力によって被せ物や構造を変えることがありますが、前歯はインプラントとは気づかれないようにきれいに治療できます。
インプラントのデメリット
このようにインプラントにはさまざまなメリットがありますが、デメリットも忘れてはなりません。ひとつは治療期間が長いことです。最近ではインプラントも進化し、かなり治療期間も短くなりましたが、それでも短くて2~3カ月、長い場合で6カ月ほどを要します。
また、インプラント治療は、歯を支えているあごの骨に人工の根っこを入れる処置なので、歯茎を開く必要があります。歯科ハンドピース用 カートリッジ、その他症例によっては他にも外科的な処置が必要になってくることもあります。骨粗鬆症や重い糖尿病の患者など、あごの骨に問題がある場合はインプラントができないこともあります。また、極端にあごの骨が痩せている場合などは、人工の骨などを使って、骨を作る処置などが必要になるケースもあります。
さらには先天的な病気などによって歯がないごく一部の場合を除き、インプラント治療を保険診療で行うことはできません。自費診療となるため、平均すると1本35万~40万円ほどの費用が必要になります。
インプラントに関連して、筆者が患者さんからよく聞かれるのは「どれくらいの耐久年数があるの?」という質問です。
インプラントは、入ってしまえば自分の歯とほぼ同じだと考えていいでしょう。手入れさえしっかりすれば自分の歯のように長く持ちます。一生といっても過言ではないかもしれません。手入れとは、毎日の歯ブラシと定期的なクリニックでのメンテナンスです。これさえ、しっかりやっていただければ本当に長持ちします。
ただ、メンテナンスを怠るとこの限りではありません。実はインプラントは、自分の歯のように歯周病(インプラント周囲炎)になることがあります。自分の歯も歯周病で抜かなければならなくなるように、インプラントも歯周病で抜かなければならなくなるケースもあります。
入れ歯のメリットとデメリット
一方で、ブリッジもインプラントもできない場合は、入れ歯という選択肢がありますが、これにもメリットとデメリットがあります。
入れ歯とは歯のなくなった部分に入れる、取り外し式の人工歯の事です。大きく分けて部分入れ歯と総入れ歯があります。また、保険内で作れるものと、保険では作れない自費のものがあります。
入れ歯は、歯が何本抜けていても骨がやせていても作れます。3、4回の通院で作れますのでインプラントほど時間はかかりません。保険が使えれば費用も安く、外して洗えたり、外科手術の必要がなかったりなどといった点もメリットでしょう。
一方で、入れ歯は慣れるまでは違和感があったり、話しにくかったりすることがあります。また、人工歯と歯茎の間に食べかすが入りやすく、食事や話している時に外れることもあります。部分入れ歯の金具が審美的でなかったり、天然歯に比べて噛む効率がかなり落ちたり、金具がかかる歯に力がかかって傷みやすかったりするのもデメリットです。合わない入れ歯を使っていると骨も痩せてしまいます。
それでも、治療費をそれほどかけたくなかったり、外科手術に抵抗があったりする人にとっては、入れ歯は有効な治療法のひとつに挙げられます。口元のハリがなく、老けて見える人やタバコをよく吸う人、短期間で処置したい人などにもお勧めしています。
逆に、入れ歯がどうしても合わなかったり、取り外し式に抵抗があったり、より自然な見た目を求めたりする人にはインプラントが合っています。喫煙もせず、あごの骨がしっかり残っていて、本物の歯に近いかみ応えを求めるような人にも適した治療法でしょう。お口の中の状態、全身の健康状態、求める仕上がりは患者さんそれぞれで異なります。何が自分に合う治療法なのかは、かかりつけの歯科医師とよく相談して決めていきましょう。
関連記事
2017年04月28日
歯磨きをしないで寝てませんか?
●夜寝る前に歯磨きをしないで寝てしまう事により。
口の健康を保つために大切な役割をしているのが唾液です。唾液の分泌量が睡眠中は減ってしまいます。だから口の中が汚れた状態で寝てしまうと、プラーク(歯垢)がたまりやすく、むし歯や歯周病にかかりやすくなりますね。
●職場には職場専用の置き歯ブラシ、外出の時には外出用の歯ブラシを。
昼食の後の休憩時間を利用して歯磨きをしましょう。
特に接客業の方は歯を磨くことで口臭予防にもなり仕事に積極的になれるのではないでしょうか。エアモーターセット
●歯間ブラシやデンタルフロスは、歯の間のお掃除のプロです。レジンセメント
歯と歯の間は、見えませんがプラークは沢山潜んでいます。(これが歯周病の大きな原因)
歯ブラシだけでは充分にプラークを落とせないため、歯間ブラシやデンタルフロスを使ってしっかりプラークを取り除きましょうね。

●お口の中を鏡で毎日覗いてみてください。
歯や歯ぐきの状態を毎日見ることで、「いつもと少し違う」といった変化がわかり、むし歯や歯周病の早期発見が自分でできるようになります。
体調が悪いときには歯ぐきも少し腫れていたり、赤くなっていたりで、健康状態を教えてくれますよ。もちろんそんなときは、丁寧に歯磨きをすることでプラークをしっかり除去しましょうね。
インプラントはいまや全世界約50カ国以上においてにも認められ利用されている、優れた医療技術です。
発祥の地であるスウェーデンでは、人口こそ日本の約15分の1ですが、普及率は6倍にも及びます。歯科技工用真空成型器日本では近年ようやく認知されはじめた技術ですが、先進諸国ではすでに市民権を得て多くの人々がこの素晴らしい技術を享受しているのです。神戸三宮インプラントセンターは、神戸の地からこの最高の医療を提供いたします。もし入れ歯や差し歯の事でお悩みでしたら、ぜひインプラントを治療の選択肢に加えて下さい。きっと世界が広がるはずです。
関連記事:インプラントのメリットは、歯の治療だけに歯とどまりません。
口の健康を保つために大切な役割をしているのが唾液です。唾液の分泌量が睡眠中は減ってしまいます。だから口の中が汚れた状態で寝てしまうと、プラーク(歯垢)がたまりやすく、むし歯や歯周病にかかりやすくなりますね。
●職場には職場専用の置き歯ブラシ、外出の時には外出用の歯ブラシを。
昼食の後の休憩時間を利用して歯磨きをしましょう。
特に接客業の方は歯を磨くことで口臭予防にもなり仕事に積極的になれるのではないでしょうか。エアモーターセット
●歯間ブラシやデンタルフロスは、歯の間のお掃除のプロです。レジンセメント
歯と歯の間は、見えませんがプラークは沢山潜んでいます。(これが歯周病の大きな原因)
歯ブラシだけでは充分にプラークを落とせないため、歯間ブラシやデンタルフロスを使ってしっかりプラークを取り除きましょうね。

●お口の中を鏡で毎日覗いてみてください。
歯や歯ぐきの状態を毎日見ることで、「いつもと少し違う」といった変化がわかり、むし歯や歯周病の早期発見が自分でできるようになります。
体調が悪いときには歯ぐきも少し腫れていたり、赤くなっていたりで、健康状態を教えてくれますよ。もちろんそんなときは、丁寧に歯磨きをすることでプラークをしっかり除去しましょうね。
インプラントはいまや全世界約50カ国以上においてにも認められ利用されている、優れた医療技術です。
発祥の地であるスウェーデンでは、人口こそ日本の約15分の1ですが、普及率は6倍にも及びます。歯科技工用真空成型器日本では近年ようやく認知されはじめた技術ですが、先進諸国ではすでに市民権を得て多くの人々がこの素晴らしい技術を享受しているのです。神戸三宮インプラントセンターは、神戸の地からこの最高の医療を提供いたします。もし入れ歯や差し歯の事でお悩みでしたら、ぜひインプラントを治療の選択肢に加えて下さい。きっと世界が広がるはずです。
関連記事:インプラントのメリットは、歯の治療だけに歯とどまりません。
2017年04月28日
虫歯・歯周病になりやすい人が怠る根本予防
「ちゃんと歯を磨いているはずなのに、すぐ虫歯になってしまう」
「これまで歯医者で診てもらうような虫歯になったことはない」
筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中で紹介していることの1つが、人によって虫歯や歯周病になりやすいタイプと、そうではないタイプに分かれることですスリーウェイシリンジ用 ノズル。
虫歯・歯周病になりやすいかどうか
いったい何が違うのでしょうか。大きく分けると4つのタイプに分類できます。
●虫歯・歯周病どちらにもなりにくいタイプ
・生まれつき免疫力が強い
・もともと歯が強い。虫歯の菌の吐き出す酸への耐性に優れている
・虫歯や歯周病の原因菌をあまり持っていない
・間食や喫煙などの虫歯や歯周病に対するリスクファクターが少ない
・毎日正しく歯磨きをしている
・お口の中への意識が高く、定期的に歯科医院で検診を受けている
●虫歯・歯周病どちらにもなりやすいタイプ
・生まれつき免疫力が弱い
・もともと歯が弱い、虫歯の菌の吐き出す酸への耐性に劣っている
・虫歯や歯周病の原因菌を多く持っている
・間食や喫煙などの虫歯や歯周病に対するリスクファクターが多い
・歯磨きを食後しないことが多い
・長い期間歯科医院に行っていない
・正しい歯磨き指導を受けたことがない
●虫歯になりやすい人のタイプ
・お口の中の細菌のなかで、虫歯菌の占める割合が多い
・歯並びが悪い
・口呼吸をしている
・唾液がネバネバする
・お菓子やジュースなど甘いモノのよく口にする
・頻繁に間食をする
・小さい頃から何度も虫歯治療を経験している
●歯周病になりやすい人のタイプ
・口腔内細菌のなかで、歯周病菌の占める割合が多い
・歯並びが悪い
・口呼吸をしている
・歯ぎしりや食いしばりをする
・頻繁に間食をする
・長い期間喫煙をしている
・不規則な生活をしている
・糖尿病を患っていて、コントロールをしていない
・歯のトラブルの経験が少なく、あまり歯科医院に行ったことがない
虫歯・歯周病のどちらにもなりやすいタイプは、お口の中の衛生状態に明らかに問題があり、食生活やお口の状態などの環境因子はよく似ています。どちらになりやすくなるかの違いは、どちらの菌を多く持っているかで決まります口腔内照明器。ただ、菌の割合を正確に判定することはできず、明確にタイプ分けするのは難しいのが実情です。上記の傾向や特徴を目安にし、ご自身の治療経験なども照らし合わせてタイプ判定してみてください。
お口の健康は保つには?
虫歯・歯周病に、なりやすいタイプの人は、できるかぎりこまめに歯科医院で検診を受けましょう歯科研磨機。このタイプの人は、本当に治療の追いかけっこのように、1つの歯を治療している間に別の虫歯ができてしまう、ということがよくあります。
虫歯・歯周病菌どちらか、またはどちらにもなっている状態で放置してしまうと、お口の中で菌が増殖し、さらに状態が悪化していきます。まずは治療が必要かどうか検査し、適切な処置を受けましょう。そして、毎日の正しい歯磨きをかかりつけの歯科医院しっかりレクチャーしてもらい、こまめに検診を受ければお口の健康は保つことができます。
虫歯になりやすいタイプの方は、虫歯の菌のお口の中での増殖も速いため、気付かぬうちに悪化させてしまうリスクがあります。こまめなかかりつけ歯科医院での検診と、正しい歯磨きはもちろんのこと、食生活の管理も重要になってきます。できれば、かかりつけ歯科医院で食材の選び方や、間食の取り方などアドバイスをしてもらうといいでしょう。
虫歯はごくごく軽度なら再石灰化という人間の治癒機能で修復したり、簡単な治療で済んだりしますが、進行して重度の虫歯になってしまうと歯の大部分を削って金属やセラミックなどで詰め物をしたり、最悪は歯を抜いたりなどという処置が必要になります。重度の虫歯は自然には治りません。
関連記事
「これまで歯医者で診てもらうような虫歯になったことはない」
筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中で紹介していることの1つが、人によって虫歯や歯周病になりやすいタイプと、そうではないタイプに分かれることですスリーウェイシリンジ用 ノズル。
虫歯・歯周病になりやすいかどうか
いったい何が違うのでしょうか。大きく分けると4つのタイプに分類できます。
●虫歯・歯周病どちらにもなりにくいタイプ
・生まれつき免疫力が強い
・もともと歯が強い。虫歯の菌の吐き出す酸への耐性に優れている
・虫歯や歯周病の原因菌をあまり持っていない
・間食や喫煙などの虫歯や歯周病に対するリスクファクターが少ない
・毎日正しく歯磨きをしている
・お口の中への意識が高く、定期的に歯科医院で検診を受けている
●虫歯・歯周病どちらにもなりやすいタイプ
・生まれつき免疫力が弱い
・もともと歯が弱い、虫歯の菌の吐き出す酸への耐性に劣っている
・虫歯や歯周病の原因菌を多く持っている
・間食や喫煙などの虫歯や歯周病に対するリスクファクターが多い
・歯磨きを食後しないことが多い
・長い期間歯科医院に行っていない
・正しい歯磨き指導を受けたことがない
●虫歯になりやすい人のタイプ
・お口の中の細菌のなかで、虫歯菌の占める割合が多い
・歯並びが悪い
・口呼吸をしている
・唾液がネバネバする
・お菓子やジュースなど甘いモノのよく口にする
・頻繁に間食をする
・小さい頃から何度も虫歯治療を経験している
●歯周病になりやすい人のタイプ
・口腔内細菌のなかで、歯周病菌の占める割合が多い
・歯並びが悪い
・口呼吸をしている
・歯ぎしりや食いしばりをする
・頻繁に間食をする
・長い期間喫煙をしている
・不規則な生活をしている
・糖尿病を患っていて、コントロールをしていない
・歯のトラブルの経験が少なく、あまり歯科医院に行ったことがない
虫歯・歯周病のどちらにもなりやすいタイプは、お口の中の衛生状態に明らかに問題があり、食生活やお口の状態などの環境因子はよく似ています。どちらになりやすくなるかの違いは、どちらの菌を多く持っているかで決まります口腔内照明器。ただ、菌の割合を正確に判定することはできず、明確にタイプ分けするのは難しいのが実情です。上記の傾向や特徴を目安にし、ご自身の治療経験なども照らし合わせてタイプ判定してみてください。
お口の健康は保つには?
虫歯・歯周病に、なりやすいタイプの人は、できるかぎりこまめに歯科医院で検診を受けましょう歯科研磨機。このタイプの人は、本当に治療の追いかけっこのように、1つの歯を治療している間に別の虫歯ができてしまう、ということがよくあります。
虫歯・歯周病菌どちらか、またはどちらにもなっている状態で放置してしまうと、お口の中で菌が増殖し、さらに状態が悪化していきます。まずは治療が必要かどうか検査し、適切な処置を受けましょう。そして、毎日の正しい歯磨きをかかりつけの歯科医院しっかりレクチャーしてもらい、こまめに検診を受ければお口の健康は保つことができます。
虫歯になりやすいタイプの方は、虫歯の菌のお口の中での増殖も速いため、気付かぬうちに悪化させてしまうリスクがあります。こまめなかかりつけ歯科医院での検診と、正しい歯磨きはもちろんのこと、食生活の管理も重要になってきます。できれば、かかりつけ歯科医院で食材の選び方や、間食の取り方などアドバイスをしてもらうといいでしょう。
虫歯はごくごく軽度なら再石灰化という人間の治癒機能で修復したり、簡単な治療で済んだりしますが、進行して重度の虫歯になってしまうと歯の大部分を削って金属やセラミックなどで詰め物をしたり、最悪は歯を抜いたりなどという処置が必要になります。重度の虫歯は自然には治りません。
関連記事
2017年04月28日
全面禁煙は経済損失と考える人の残念な論理
昨年来、厚生労働省を中心に進められている健康増進法改正案の概要に、複数の業界団体が反対声明を出していることが話題になっている。この改正案では飲食店での禁煙化が盛り込まれており、違反した場合は飲食店、喫煙者ともに罰せられる。同法案は1月20日招集の通常国会を通過すれば、今年前半にも施行される可能性があり、それに先んじての動きだ。
健康増進法改正案では、これまで努力義務であった小中学校や官公庁、飲食店、駅・空港などでの禁煙が義務化され、罰則についても科料が加えられることとなった。なお、飲食店と交通拠点に関しては、いずれも喫煙室の設置が認められている。
公共の場における喫煙に関しては、受動喫煙の危険性といった直接的な健康被害ももちろん大きなポイントだ。子どもが立ち入る可能性が高い場所ならばなおさらだが、問題は受動喫煙だけではない。
直接の健康被害ではないため、“健康増進”という部分からは離れるが、喫煙者自身は気づかない悪臭などの問題も大きい。喫煙率が19.3%(男性32.2%、女性8.2%、厚労省調べ)まで減少している現在の日本社会を鑑みるならば、“料理”という商品の価値を損ねる悪臭を発する喫煙を飲食店で禁止することは、極めて合理的と言えるだろう。

外食産業が「反対集会」を決起
ところが、このニュースに対して外食産業などが集まり、一律の規制に「反対集会」を開いたことが議論の扉を開いた。
中でも飲食店業界の反発は大きい。1月12日に開かれた受動喫煙防止強化に対する緊急集会において、全国飲食業生活衛生同業組合連合会、日本フードサービス協会といった団体が意見を出したが、彼らの意見は実にシンプル歯科用インプラント装置。反対する団体の主張内容はどこも似通っている。
すなわち、法的に認められた“たばこ”という嗜好品を、たのしむ人も、たのしみたくない人も、それぞれに互いが嫌な思いをすることなく共存できる“分煙先進国ニッポン”を目指すべき――というものだ。これまでも飲食業界では、分煙の徹底や店頭でのステッカー張り付けによる喫煙可否の表示などを進めてきており、一律に禁止することで「廃業に追い込まれる店もある」と経済的にマイナスとの意見も出されていた。
オススメ商品をご覧ください:
http://www.athenadental.jp/category-2080-b0-エアモーターセット.html
しかしながら、こうした反対意見の多くは合理性を欠いていると言わざるをえない。社会全体で見た場合、喫煙を許容するほうが経済損失が大きいと考えられるからだ。
日本におけるたばこ関連の税金は近年ほぼ一定で、年間2兆円を超える程度である(地方税含む)アマルガムミキサー。2015年は2兆1500億円であり、これにたばこの売り上げに伴う消費税2900億円を加えた2兆4400億円が、たばこ関連の税収ということになる。その税率は63.1%にも及ぶ。
しばしば、こうした数字が喫煙を正当化するために用いられるが、たばこによる損失は税収を上回ると考えられる。
確かに日本において、たばこは“嗜好品”として供される法的に認められた商品である。「ニコチンによる依存性は微弱であり、アルコールなどよりはるかに低く自己責任」との判例があることも背景としてあるだろう。
世界でのたばこに対する認識とは
筆者は多様な国や地域に取材で出かけているが、日本はたばこに対して寛容な国のひとつだ。
しかしながらグローバルでのたばこに対する認識は異なる。1995年、米国における裁判で、元たばこ会社役員が「ニコチンに依存性があることを知って販売しており、またニコチンへの依存度を高める添加物を使っていた」と認めたことで、たばこの健康被害がクローズアップされて以来、依存性に関しても健康被害に関しても厳しい目が向けられている。
米国CDC(Centers for Disease Control and Prevention:米国疾病予防管理センター)の資料によると、肺、口腔、咽頭といった喫煙に関連する部位のがん、および冠状動脈性心臓病は喫煙率の低下とともに有意に低下する相関関係が認められているという。
同様の研究は数多く見つかるが、いずれにしろたばこに健康被害があることは、喫煙者も非喫煙者も承知しており、今さら過去の事例を持ち出す必要はないだろう。
やや古い数字ではあるが、医療経済研究機構による1999年の推計として年間7兆3000億円の損失が喫煙によりもたらされているとの報告がある。この数字は平均の労働寿命が短くなることによる損失が5兆8000億円も見込まれており、合計の金額には疑問がある。
しかし、仮に上記の見積もりが過大であり、“たばこ販売”による経済効果と、それに対する医療費増大や寿命短縮などのマイナスがほぼ同じ程度だとしよう。だが1999年以降、次々に喫煙および受動喫煙による健康被害が確実であるとの研究結果が発表されている。腹部大動脈瘤や歯周病はその代表例だが、国立がん研究センターは脳卒中や心筋梗塞に関しても、受動喫煙だけで有意にその確率が上昇するとしている。
すなわち、1999年当時の医療費増大に関する見積もりは過小だったと考えられよう。加えるならば、飲食店などが全面禁煙化に反対をしているものの、全面禁煙化により外食ビジネスは伸びるという見方もある。
国内の事例をひもとくと、かつて居酒屋チェーンの「和民」が2005年に全面禁煙を実施した際には、ファミリー層の利用者は増加したものの、一般サラリーマンや宴会需要が減少。売り上げがマイナスとなったため、分煙化へと舵を切った経緯がある。
しかし当時に比べ現在では成人喫煙率は10%も低下した。一貫して喫煙率が低下し続けていることを考慮すれば、社会的な影響は少ない。
そのうえ、“全面的に”禁止になるのだから利用者に選択肢はない。どの店に入ろうと店内ではたばこを吸えないのだから。
関連記事
健康増進法改正案では、これまで努力義務であった小中学校や官公庁、飲食店、駅・空港などでの禁煙が義務化され、罰則についても科料が加えられることとなった。なお、飲食店と交通拠点に関しては、いずれも喫煙室の設置が認められている。
公共の場における喫煙に関しては、受動喫煙の危険性といった直接的な健康被害ももちろん大きなポイントだ。子どもが立ち入る可能性が高い場所ならばなおさらだが、問題は受動喫煙だけではない。
直接の健康被害ではないため、“健康増進”という部分からは離れるが、喫煙者自身は気づかない悪臭などの問題も大きい。喫煙率が19.3%(男性32.2%、女性8.2%、厚労省調べ)まで減少している現在の日本社会を鑑みるならば、“料理”という商品の価値を損ねる悪臭を発する喫煙を飲食店で禁止することは、極めて合理的と言えるだろう。

外食産業が「反対集会」を決起
ところが、このニュースに対して外食産業などが集まり、一律の規制に「反対集会」を開いたことが議論の扉を開いた。
中でも飲食店業界の反発は大きい。1月12日に開かれた受動喫煙防止強化に対する緊急集会において、全国飲食業生活衛生同業組合連合会、日本フードサービス協会といった団体が意見を出したが、彼らの意見は実にシンプル歯科用インプラント装置。反対する団体の主張内容はどこも似通っている。
すなわち、法的に認められた“たばこ”という嗜好品を、たのしむ人も、たのしみたくない人も、それぞれに互いが嫌な思いをすることなく共存できる“分煙先進国ニッポン”を目指すべき――というものだ。これまでも飲食業界では、分煙の徹底や店頭でのステッカー張り付けによる喫煙可否の表示などを進めてきており、一律に禁止することで「廃業に追い込まれる店もある」と経済的にマイナスとの意見も出されていた。
オススメ商品をご覧ください:
http://www.athenadental.jp/category-2080-b0-エアモーターセット.html
しかしながら、こうした反対意見の多くは合理性を欠いていると言わざるをえない。社会全体で見た場合、喫煙を許容するほうが経済損失が大きいと考えられるからだ。
日本におけるたばこ関連の税金は近年ほぼ一定で、年間2兆円を超える程度である(地方税含む)アマルガムミキサー。2015年は2兆1500億円であり、これにたばこの売り上げに伴う消費税2900億円を加えた2兆4400億円が、たばこ関連の税収ということになる。その税率は63.1%にも及ぶ。
しばしば、こうした数字が喫煙を正当化するために用いられるが、たばこによる損失は税収を上回ると考えられる。
確かに日本において、たばこは“嗜好品”として供される法的に認められた商品である。「ニコチンによる依存性は微弱であり、アルコールなどよりはるかに低く自己責任」との判例があることも背景としてあるだろう。
世界でのたばこに対する認識とは
筆者は多様な国や地域に取材で出かけているが、日本はたばこに対して寛容な国のひとつだ。
しかしながらグローバルでのたばこに対する認識は異なる。1995年、米国における裁判で、元たばこ会社役員が「ニコチンに依存性があることを知って販売しており、またニコチンへの依存度を高める添加物を使っていた」と認めたことで、たばこの健康被害がクローズアップされて以来、依存性に関しても健康被害に関しても厳しい目が向けられている。
米国CDC(Centers for Disease Control and Prevention:米国疾病予防管理センター)の資料によると、肺、口腔、咽頭といった喫煙に関連する部位のがん、および冠状動脈性心臓病は喫煙率の低下とともに有意に低下する相関関係が認められているという。
同様の研究は数多く見つかるが、いずれにしろたばこに健康被害があることは、喫煙者も非喫煙者も承知しており、今さら過去の事例を持ち出す必要はないだろう。
やや古い数字ではあるが、医療経済研究機構による1999年の推計として年間7兆3000億円の損失が喫煙によりもたらされているとの報告がある。この数字は平均の労働寿命が短くなることによる損失が5兆8000億円も見込まれており、合計の金額には疑問がある。
しかし、仮に上記の見積もりが過大であり、“たばこ販売”による経済効果と、それに対する医療費増大や寿命短縮などのマイナスがほぼ同じ程度だとしよう。だが1999年以降、次々に喫煙および受動喫煙による健康被害が確実であるとの研究結果が発表されている。腹部大動脈瘤や歯周病はその代表例だが、国立がん研究センターは脳卒中や心筋梗塞に関しても、受動喫煙だけで有意にその確率が上昇するとしている。
すなわち、1999年当時の医療費増大に関する見積もりは過小だったと考えられよう。加えるならば、飲食店などが全面禁煙化に反対をしているものの、全面禁煙化により外食ビジネスは伸びるという見方もある。
国内の事例をひもとくと、かつて居酒屋チェーンの「和民」が2005年に全面禁煙を実施した際には、ファミリー層の利用者は増加したものの、一般サラリーマンや宴会需要が減少。売り上げがマイナスとなったため、分煙化へと舵を切った経緯がある。
しかし当時に比べ現在では成人喫煙率は10%も低下した。一貫して喫煙率が低下し続けていることを考慮すれば、社会的な影響は少ない。
そのうえ、“全面的に”禁止になるのだから利用者に選択肢はない。どの店に入ろうと店内ではたばこを吸えないのだから。
関連記事